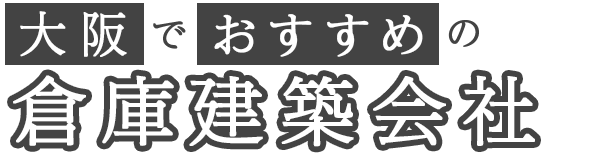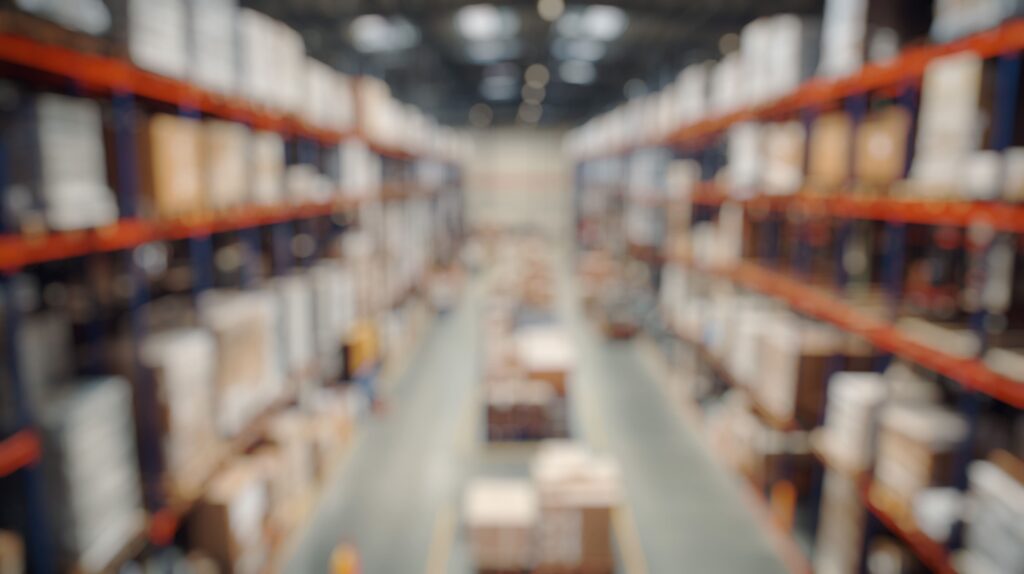
日本は地震大国として知られており、現代でも大地震が定期的に起こっています。倉庫や工場の建築においても、耐震性はスタッフの安全性確保などの観点から欠かせない要素です。今回は倉庫や工場の耐震性について、具体的な基準や診断が必要な建物の条件、耐震性をアップさせる対策などを解説するため、ぜひ参考にしてください。
倉庫に定められた耐震基準とは
地震大国の日本において、建築物の耐震性は非常に重要な要素です。住宅や店舗はもちろん、倉庫・工場についても一定以上の耐震性が求められます。ここでは、倉庫の建築における耐震基準について詳しく解説します。倉庫を対象とした特別な基準は存在しない
倉庫や工場には耐震性に関する個別の定めがあるわけではなく、すべての建築物に対して求められている最低限の基準を満たせばよいとされているのが特徴です。耐震基準は建築基準法で定められており、要件を満たさない建物は建築できないことになっています。倉庫に適用される耐震基準は2種類ある
現在適用されている耐震基準は新耐震基準と呼ばれ、震度6強〜震度7の大地震が起こっても倒壊しない程度の耐震性が求められます。新耐震基準が適用されるようになったのは1981年6月であり、木造住宅に関しては2000年以降さらに厳しい基準が設定されました。また、新耐震基準が施行される以前に建築確認を受けていた建物に関しては、旧耐震基準が適用されています。そもそも耐震基準は関東大震災による被害をきっかけとして定められたのが始まりであり、建築基準法の制定とともに旧耐震基準が設けられるようになりました。
旧耐震基準では、震度5強の地震でも建物が倒壊しないこと・建物に破損が見られても補修により引き続き建物を使用できることが求められています。
倉庫や工場においても、1981年5月末までに建築確認を受けたものに関しては旧耐震基準が、1981年6月以降に建築確認を受けたものに関しては新耐震基準が適用されています。
倉庫も耐震診断が求められる?
建築基準法の耐震基準を満たしているかどうかは、耐震診断によって判断されるのが通常です。1981年6月以降に建築された倉庫は建築確認の段階で新耐震基準を満たしていることが確認されていますが、1981年5月末までに建築確認を受けた旧耐震基準の倉庫については、耐震診断を実施しなければ新耐震基準を満たしているかどうかを判断できません。
しかし、旧耐震基準が適用されている倉庫のすべてに対して耐震診断が求められるわけではなく、特定の条件に当てはまる場合にのみ診断が必要です。ここでは、耐震診断が必要となる倉庫・工場の条件について詳しく解説します。