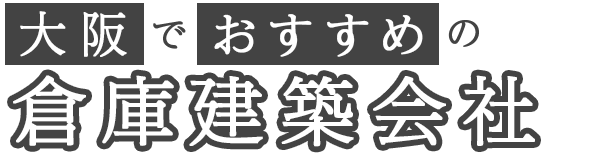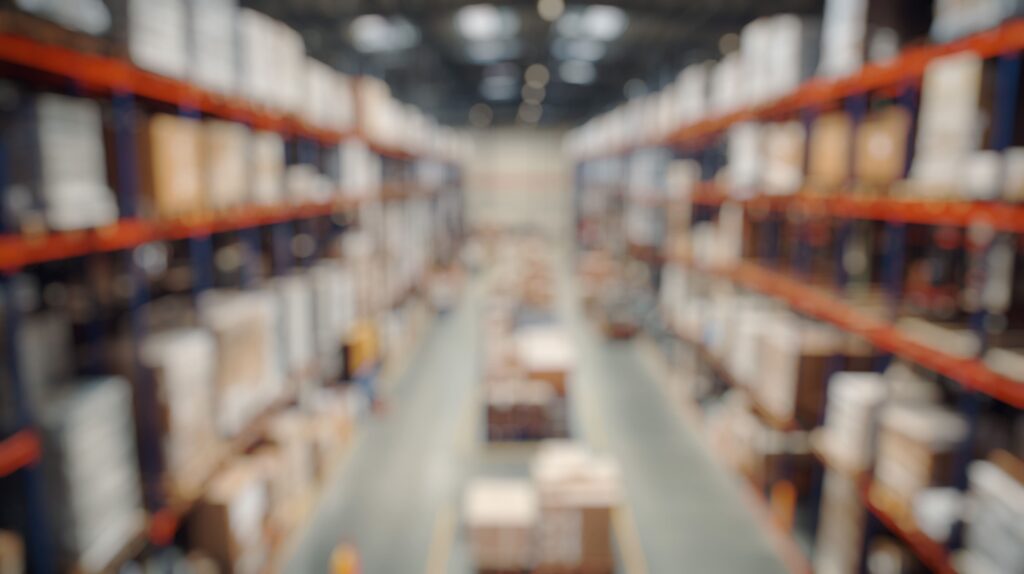新たに倉庫を建てる際には、法律や地域ごとの規制を理解することから始めましょう。倉庫は事業の拡大や防災対策に役立つ重要な建物ですが、建築基準法や用途地域、建ぺい率や容積率といった多くの条件をクリアしなければなりません。この記事では、倉庫建築にあたって押さえておきたい注意点と、建築までの流れをわかりやすく解説します。
こんなときに倉庫が役立つ!倉庫建築のメリット
事業の規模が拡大したり、取り扱う商品や資材の量が増えたりすると、自社専用の倉庫が必要になるケースは少なくありません。倉庫を新築することで、業務効率や保管体制を大きく改善できる可能性があります。倉庫は単なる荷物置き場ではなく、用途や扱う物品によって最適な種類を選ぶことで、事業の成長を後押しする存在となるでしょう。
普通倉庫とは
「普通倉庫」と呼ばれる倉庫の分類の中では、目的ごとに種類が定められています。代表的なのが1類から3類までの倉庫です。1類倉庫は、もっとも厳しい基準が設けられており、多様な物品を幅広く保管できる高グレードな施設です。危険物や低温保管が必要な品目を除けば、多くの荷物を安全に収納できます。これに対して2類倉庫は耐火性能を必要としない倉庫で、保管できる品目の範囲はやや限定されます。さらに3類倉庫になると、防火や防湿の基準も不要となり、湿度や温度変化に強い陶磁器やガラス製品などを保管するのに適した倉庫です。
貯蔵槽倉庫
扱う品目によっては、普通倉庫以外の専門的な倉庫を選ぶ必要もあります。たとえば液体やバラ状の穀物を大量に収容する場合に必要なのが、タンクやサイロといった設備を備える貯蔵槽倉庫です。倉庫そのものに高い側壁強度が求められるため、通常の倉庫とは異なる設計が採用されます。危険物倉庫
危険物や高圧ガスを扱う場合は、消防法や高圧ガス保安法など複数の法律に適合した危険品倉庫が必要です。これらは安全性が最優先されるため、設計段階から専門的な知識と法規制への対応が欠かせません。冷蔵倉庫
食品や医薬品など、低温での管理が不可欠な物品に向いているのが冷蔵倉庫です。冷蔵倉庫は保管する品目や温度帯に応じて細かく等級が分かれており、食肉や水産物、冷凍食品などを10度以下で安定的に管理できます。倉庫が完成するまでの流れ
倉庫を新築する際には、完成までにいくつもの工程を経る必要があります。現場では安全性や精度を確保するために、段階ごとに検査や確認が実施されるためです。ここでは、倉庫完成までの流れを順を追って見ていきましょう。敷地調査
着工前に地盤調査を行い、複数の地点で地盤の固さを測定します。地盤の状態に応じて補強が必要かどうかを判断し、安定した基礎を築く準備を整えます。基礎工事
敷地を掘削し、地盤をしっかり締め固めた上で捨てコンクリートを打設します。これは、基礎の鉄筋や型枠を正確に組み立てるための下地づくりです。その後、基礎の骨格となる鉄筋を組み立て、配置に偏りや誤りがないか検査員が確認します。さらに、生コンクリートを流し込む際には監督が立ち会い、品質や施工状況を細かくチェックします。
腰壁工事
鉄筋を組み上げ、再び検査員が配筋の正確さを確認します。コンクリートを打設する際には、左官職人が表面をていねいに仕上げ、鉄骨を安定して据え付けられるよう水平を確保します。こうして土台が整うと、いよいよ建物の骨格を形作る鉄骨建方の開始です。大型クレーンで鉄骨を吊り上げ、ボルトで固定しながら組み立てていく作業は、倉庫建築の大きな見せ場です。
屋根・外壁工事
屋根材を設置し、完成したあとで外壁を取り付け、外部検査で施工に不備がないかを確認します。内部工事
まずは土間コンクリートを施工するための下準備として、砂利を敷き詰めて高さを調整し、転圧をかけて地面を固めます。その上に湿気防止のポリフィルムを敷き、鉄筋を組み立てます。土間は面積が広いため、ひび割れを防ぐ補強を柱周りに施すことがポイントです。配筋後には検査員のチェックを受け、合格すればコンクリートを打設します。
最終調整・補修
社内検査、消防検査や完了検査などを経て、最終的に施主による検査を受けます。これらをすべてクリアして初めて、倉庫の引き渡しとなります。倉庫の新築前に確認すべき注意点も解説!
新築で倉庫を建てようと考えたとき、多くの人が不安に感じるのが「どこに建てられるのか」「どんな法律に従う必要があるのか」という点です。ここでは、計画を進める前に押さえておきたい注意点を解説します。建築基準法
建物の安全や衛生、都市計画の調和を目的とし、敷地や構造、設備、用途について最低限守らなければならない基準を定めています。倉庫は不特定多数が利用する「特殊建築物」に該当し、火災防止や避難の安全確保のために厳しい規制がかかります。主要構造部の制限など、通常の住宅とは異なる基準に注意が必要です。用途地域
倉庫はどの土地でも建てられるわけではなく、都市計画によって指定された用途地域に従う必要があります。「自家用倉庫」と「倉庫業倉庫」では建設可能な地域が異なるため、事前の確認が欠かせません。その他の規定にも従う
建ぺい率や容積率、高さ制限や斜線制限といった規定も考慮しなければなりません。建ぺい率は敷地に対してどの程度の面積を建築に充てられるかを示し、容積率は敷地面積に対する延べ床面積の上限を定めています。高さや斜線制限は、周辺の景観や採光、通風を守るために設けられており、地域ごとに異なる基準があります。これらを無視すると、計画が認可されず、工事が進められない事態になりかねません。